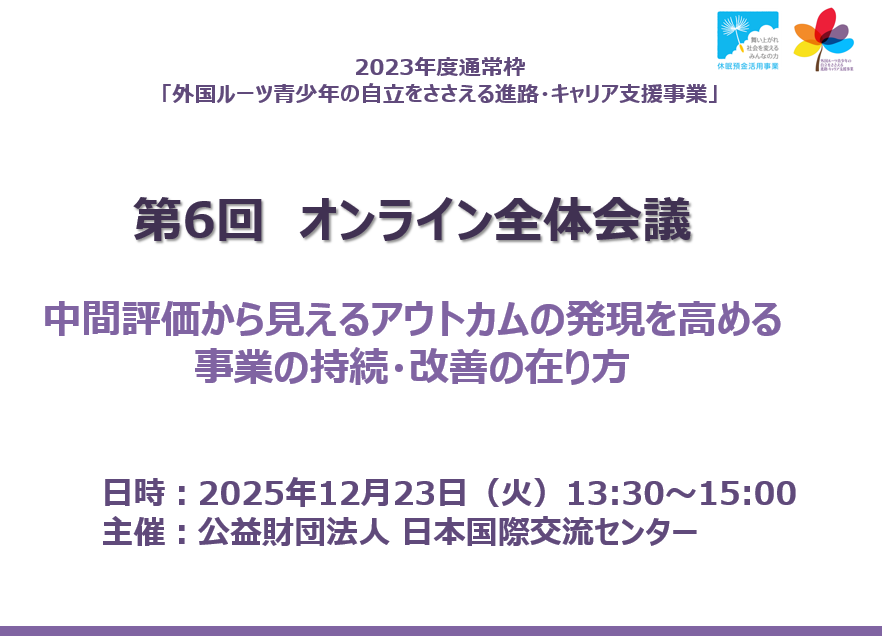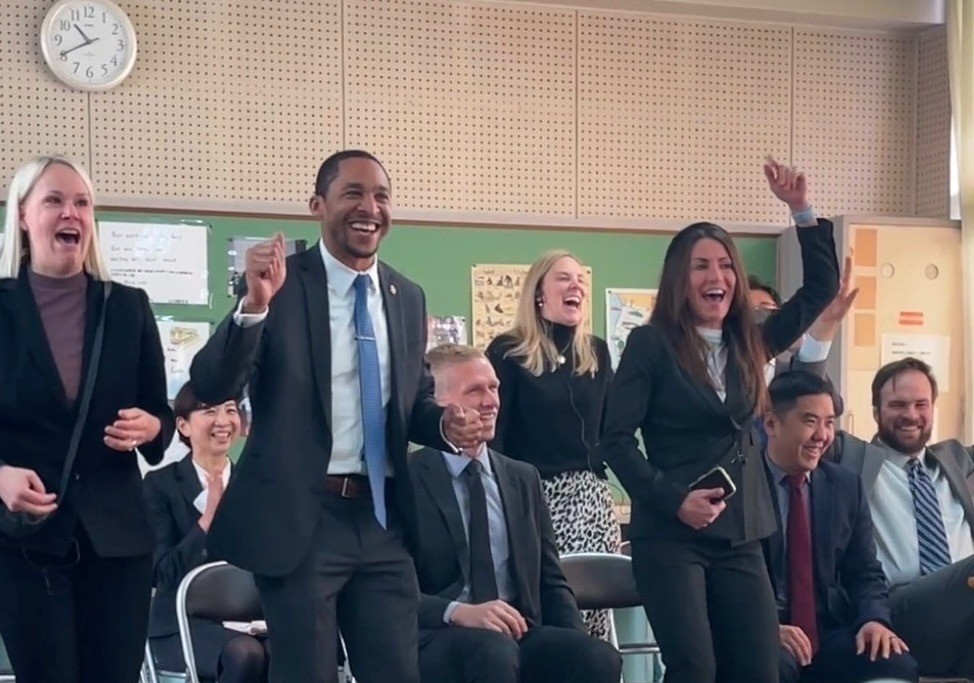ページを探す
日英21世紀委員会 第41回合同会議

2025年3月14日~16日にかけて、日英21世紀委員会第41回合同会議が、英国ロンドン及びケンブリッジシャー州フォーダム・アビーで開催されました。
英国と日本から政治家、研究者、ジャーナリスト、企業経営者など約40名の参加を得て、両国の政治・経済、地政学的課題、非感染症および感染症対策におけるユニバーサルヘルスケアの重要性、両国の科学技術協力と大学間パートナーシップ、IT、サイバー、AIの最新動向とその影響、エネルギー安全保障と気候変動への対応における協力促進など、両国が直面する諸課題について討議が行われました。フォーダムでの合同会議に先立ち、ロンドンでは、英首相官邸にてアンジェラ・レイナー副首相を表敬したほか、外務英連邦開発省主催レセプション、鈴木浩駐英日本大使主催昼食会が開催されました。
本会議のステートメント(提言)、詳細プログラム及び参加者は以下のとおりです。
和文ステートメント | 英文ステートメント
プログラム | 参加者
[追記] 2025年4月10日、総理大臣官邸にて、日本側座長を務める木原誠二衆議院議員より石破総理大臣に対し、第41回合同会議のステートメント(提言)を手交いたしました。
日英21世紀委員会第41回合同会議(日本側座長による総理報告会) (外務省ウェブサイト)


討議概要
セッション1:日英両国の政治・経済の現状
日英両国の政治・経済動向について議論が行われた。英国では、2024年選挙で労働党が勝利したものの、国内政治の分裂化傾向が高まっている。以前は有権者の約97%が労働党か保守党のいずれかに投票していたが、最近の支持政党調査では、労働党24%、保守党22%、リフォームUK23%、自由民主党/緑の党が24%と、4つに分かれている。有権者の最大懸念事項が経済、移民、住宅不足問題であることに変わりはない。日本も同様、政情は不透明。自公連立与党は衆議院において実質70年間維持してきた過半数を失い、2025年には参院選を迎える。日本政府は、インフレ、地方経済成長・インフラへの投資、輸出ポテンシャルの拡大への取り組みに注力する必要がある。日英両国の政治におけるポピュリズムの本質および、インフレ、疎外感、アクセスの欠如、経済格差などに関連する不満の原因について議論した。信頼できるメディアソースが引き続き必要であるが、従来型の政治に「見捨てられてきた」と感じる人々が抱える問題にも向き合っていくことが重要である。
セッション2:非感染性/感染性疾患への取り組みにおけるユニバーサルヘルスケアの重要性
グローバルヘルス課題への取り組みにおける日英協力の可能性をテーマに、感染性疾患への具体的取り組み事例や、「ワンヘルス」総合的アプローチの利点が紹介された。そうしたアプローチが、第三諸国におけるよりレジリエントな保健制度の構築やユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)にいかなる貢献を果たし得るか検討した。様々な分野や社会レベルの枠を超えた協力の可能性について議論を行った。複数のレイヤーで構成されるグローバル・ヘルス・ガバナンス体制について議論するとともに、米国新政権によるグローバルヘルスへの資金拠出停止に伴う空隙を日英両国でどうのように補うことが可能か検討した。米国の新たな政治的制約によって、今後、二国間協力や、志を同じくする少数国間の「ミニラテラル」な協力などのアプローチも検討していくことになるかもしれないが、ヘルス分野においてグローバルな協力が引き続き重要であることに変わりはないことを示した。
セッション3:科学技術協力および大学パートナーシップ
日本の科学技術を巡る状況は新たな時代の幕開けを告げている。近年の急速な国家投資の拡大を背景に、量子コンピューティング、AI、核融合エネルギー、バイオエンジニアリングなどの重要技術分野だけでなく、近年の大学改革以後、人材開発拠点としての役割を強化している大学にも投資が向けられている。特筆すべき変化は、学術研究への投資に関して、経済産業省、総務省、防衛省の関与が高まっている点。国家安全保障の強化のみならず最先端科学技術イノベーションの共同研究の推進という点でも、より強固な日英パートナーシップが果たす役割は極めて大きい。日本の大学6️校と英国の大学6校が参加するRENKEI Network(日英大学間連携プログラム)など、大学主導の連携プログラムも複数存在する。米国の資金拠出に政治的制約が課されるようになったことを踏まえ、英国、日本その他諸国にとっては、共通の価値観に基づく研究事業を推進する機会が生まれている。委員会メンバーは、防衛・宇宙関連技術の研究協力を支持した。
セッション4:地政学的課題
米国新政権とその大規模な政策の変化が日英両国にもたらす影響とリスクについて詳細に議論した。我々がこれまで慣れてきた戦後世界秩序へと回帰する望みは薄い。米国政権内は孤立主義者、抑制主義者が優勢であり、国外にリソースを割くことに消極的である。欧州からアジアへの軸足の変化は、前民主党政権ですでに始まっていた。現在の米国政策がもたらすであろう従来の世界秩序の崩壊という流れは、政権交代後も止まらない可能性が高い。日英両国は、新たな秩序構築の可能性を拓くグローバルな議論において、協調したリーダーシップを発揮していくべきである。報道と学問の自由を守ることの重要性について、気候や貿易などの問題について英国、日本とその他同盟国間が共通の利害を有している点を指摘した。既存の同盟関係に対する米国のコミットメントの信頼性や、拡大核抑止の信頼性に大きな疑念があることを踏まえ、核拡散リスクの増大、自由民主主義政府と政治的・法的規範の脆弱性、国際的な外交・経済・安全保障協力体制の弱体化などの問題を指摘した。戦後の米国同盟関係を自明のことと考えてはならず、リスク軽減に向けて日英両国がいかに協力できるか検討した。日英両国は、米国との対話と同盟関係を維持しつつ、志を同じくする国々との同盟関係やパートナーシップ構築に努めるべきである。
セッション5:情報、サイバーおよびAI
過去3年間、AIモデルは急速な進化を遂げ、世界の注目は、AIの安全性から国際競争力へと移っている。AIモデルは今後2年以内に次の段階へと進化し、ワークフローの自動化やアイデア創出が可能になるだろう。大手AI企業が優位な状況は続くが新興企業にも勝機がないわけではない。AIの発展ペース、安全性とセキュリティを確保するために規制を導入する必要性について議論した。教育分野におけるAI使用も政策投入が急がれる課題である。サイバーセキュリティの強化は国防・安全保障と一体をなし、一層重要となっている。サイバーセキュリティの場合、脅威は既存の法的枠組みの想定を超えて発展し悪質化しており、喫緊の対応が必要である。この分野での日英協力は相互にメリットをもたらすものであり、その必要性も高まっている。サイバー脅威は国境や産業の壁を超え、官民を問わずターゲットになる、いわゆる「グレーゾーン」においてますます増加している。セキュリティ・クリアランス(適正評価)や能動的サイバー防御の枠組みを導入した日本の取り組みを評価する一方で、日本は自国のサイバーセキュリティ能力を高めるべく、英国をはじめとするパートナーと緊密に協力する必要がある。こうした協力には国家の技術・人材開発も盛り込むべきであり、学術界も含む強固なサイバーセキュリティーエコシステムの構築につながるものでなければならない。
セッション6:気候変動とエネルギー安定供給
民間部門が採用する気候変動対策やエネルギー安定供給対策および、行政による政策支援について検討した。日本の第7次エネルギー基本計画では、エネルギー需給構造の転換を経済成長と連動させるべく、産業政策の強化を謳っている。同時に、エネルギー安定供給への注力および経済効率性の向上という原則への立ち返りを図ろうとしている。電力需要増を満たすためには、再生可能エネルギーと原子力を組み合わせることが必要であり、エネルギーは地政学的アジェンダの中心的課題である。英国は、2030年までにクリーン電力システムを達成するという野心的目標を掲げ、電力システムの脱炭素化に関して大きな進展を見せており、電化はネットゼロ達成に極めて重要であるが、需要は予想を下回っている。新興国において低炭素エネルギーと再生可能エネルギー両方のプロジェクトを支援する「ブレンデット・ファイナンス」の重要性について賛同を得た。一方、原子力エンジニア不足や原発導入の影響要因となる生活費の高騰問題を踏まえ、目標がどの程度現実的なものか疑問の声も上がった。日英両国が気候変動への活動で引き続き自治体や民間部門をリードすること、再生可能エネルギーへの移行に市民が参画するよう積極的に働きかけていくことへの期待を示した。
アンジェラ・レイナー副首相表敬

2025年3月13日 アンジェラ・レイナー副首相への表敬(於 英首相官邸 ダウニング10)


日英21世紀委員会は、1984年に中曽根康弘首相とマーガレット・サッチャー首相との間で合意され、翌85年に正式に設置された民間レベルの政策対話フォーラムです。年1回の合同会議において両国委員が議論し日英関係のあり方についての提言をまとめ、それぞれの首相に報告しています。(外務省委託事業)
日英21世紀委員会に関する活動報告
Copyright © Japan Center for International Exchange (JCIE)