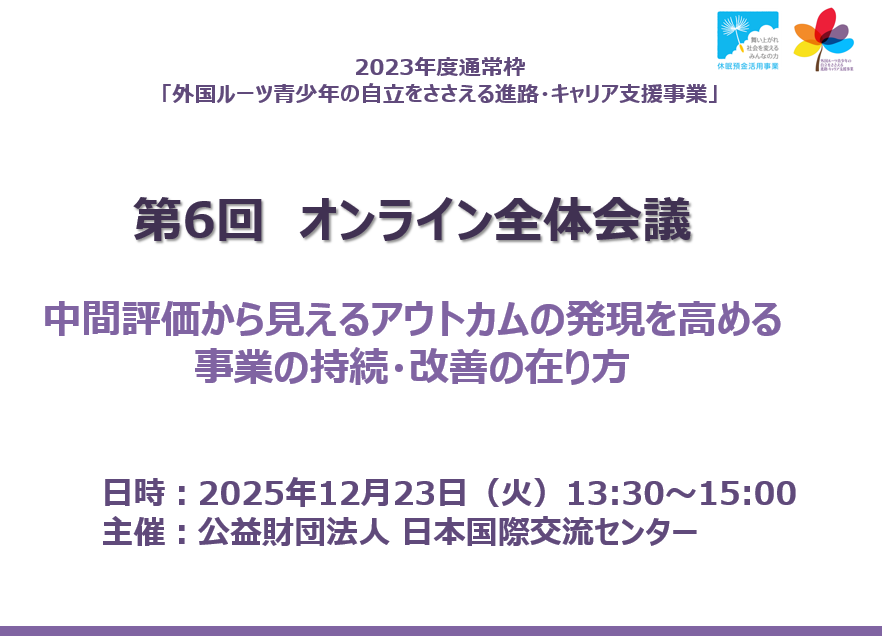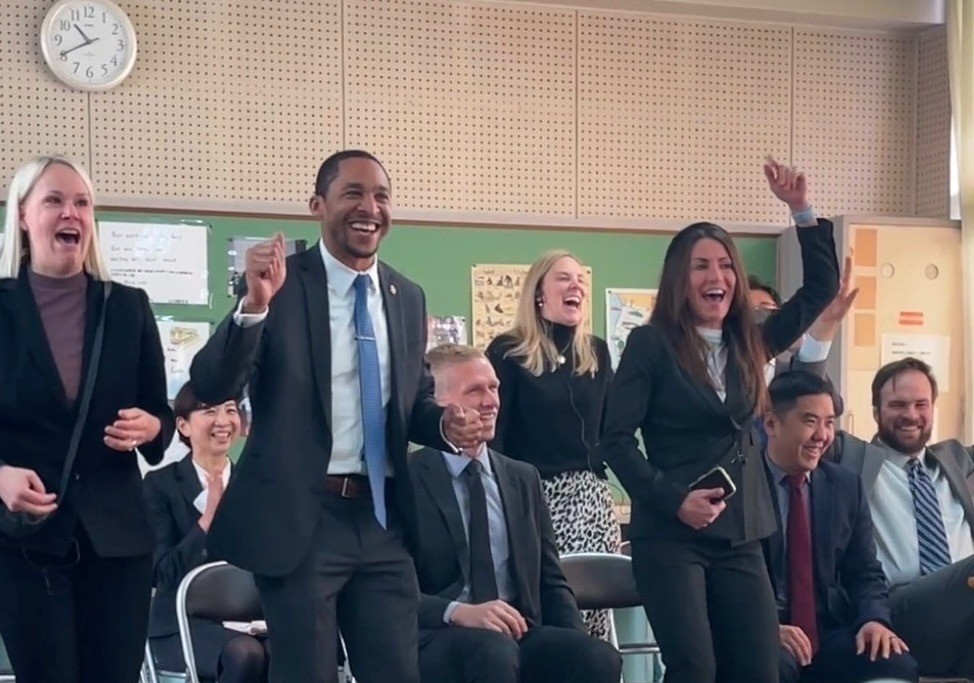ページを探す
日・ASEAN保健協力に係るマルチステークホルダー対話の可能性に関する調査

2023年、日・ASEAN友好協力50周年に際して採択された「日・ASEAN友好協力に関する共同ビジョン声明」では、保健医療を「未来の経済社会の共創」における優先事項として位置付け、この分野における協力の重要性を強調しています。こうした流れを受け、日本国際交流センター(JCIE)は、日本とASEANが共通の保健課題に対する解決策の共創を促進するため、政府、研究者、市民社会、そして民間セクターを結集したマルチステークホルダー対話プラットフォームの構築を検討しています。
この取組の一環として、公衆衛生に関わる専門人財を養成する長崎大学大学院プラネタリーヘルス学環DrPHプログラム(長崎DrPHプログラム)の協力を得て(注)、保健課題における日本とASEANの協力において、どのようなテーマを優先して取り上げるべきかという調査を委託しました。その結果、非感染性疾患(noncommunicable diseases: NCDs)の予防・対策の強化、デジタルヘルスにおける諸課題の改善、そして、デジタルツールを活用して「ウェルネス」を推進することが特定されました。同調査の過程では、JCIEと長崎DrPHプログラムとの共催でセミナー(下記参照)も開催し、そこでの議論も踏まえ、最終報告書が取りまとめられました。
(注) 本調査は、長崎大学大学院プラネタリーヘルス学環の「2025年度DrPH短期実務研修(Nagasaki Public Health Consulting)」として、JCIEが受入組織となって実施したものです。
長崎DrPHプログラム チームメンバー (アルファベット順)
Oluwaseun Adebayo Adewunmi (from Nigeria)
Due Emmanuel Awai (from Nigeria)
Prakash Chandra Bhatta (from Nepal)
Chanida Ekakkararungroj (from Thailand)
Ruth Purisima Gonzalez Sanchez (from Mexico)
Mavis Sakyi (from Ghana)
調査報告書
ASEAN-Japan Health Dialogue: Strategic Recommendations for Public-Private Collaboration
(ASEAN-日本 保健医療対話:官民連携のための戦略的提言)
※長崎大学大学院プラネタリーヘルス学環のウェブサイトに移動します。
本調査は、日本とASEANに共通しており、官民の連携によって解決の糸口が見いだせる可能性がある課題を抽出し、日・ASEAN保健対話の方向性についての提言を導き出そうとするものです。文献調査や様々なステークホルダーへのインタビュー等を通じて、以下のような課題への取組の必要性が示されました。
優先課題1: 非感染性疾患(NCDs)
ASEAN諸国でも大きな健康負荷となっている非感染性疾患(NCDs)への対策の必要性が浮かび上がっています。近年、「健康の社会的決定要因(Social Determinants of Health: SDH)」のみならず、「健康の商業的決定要因(Commercial Determinants of Health: CDH)」という視点が取り上げられるようになってきました。NCDsを予防するためには、CDHに対し、国を超えて地域全体で対策をしていくことが求められます。しかし、病原体が国境を越えて広がる感染症と異なり、NCDsそのものは「非感染性」であり、個人の生活習慣にも影響されることから、NCDs対策には必ずしも政治的に高い関心が向けられてきませんでした。対策を強化するためには、「治療」から「予防」に重点をシフトさせることが重要です。また、世界銀行と世界保健機関(WHO)が共同で日本に設置する「UHCナレッジハブ」も活用しながら、「ヘルス税」(健康に悪影響のある嗜好品や食品等への課税)の導入や革新的資金調達メカニズムの創出、民間セクターとのパートナーシップ促進などを通じて、知識を共有しつつ、持続可能な保健財政を構築していくことも求められます。
(参考) 世界保健機関(WHO), Commercial Determinants of Health(健康の商業的決定要因), Health taxes(ヘルス税)
世界銀行, UHCナレッジハブ:ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)の持続可能な資金調達を支援
優先課題2: デジタルヘルス
医薬品や医療機器に関する規制のみならず、保健医療データに対する規制やガバナンスのあり方が国によって異なること、場合によっては不明瞭であることで民間企業が市場参入する際に障壁となり得ます。また、断片化されたシステムによって相互運用性が阻まれていることも課題として挙げられます。他方、データの収集・活用に際しては、プライバシーやセキュリティ対策について、人々から必ずしも信頼されているとは言えない状況もあり、データの取扱いに関する倫理や規制のあり方についても検討が必要です。デジタルヘルス強化の先進的事例や成功事例などを積極的に共有すること、地域全体でデータの相互運用が可能となるようなガバナンスの仕組みを共にデザインしていくことなどが求められます。
デジタルツールを活用した「ウェルネス」の推進
調査報告書では、このような課題も踏まえつつ、NCDs予防のためにデジタル技術をさらに活用することを提案しています。近年、スマートフォンのアプリや、人工知能(AI)技術などを活用した医療機器プログラム(Software as a Medical Device: SaMD)が普及してきていることは新たな可能性を拓くものですが、一方で、国や地域によってデジタルインフラの格差があり、また、それとも相まって保健医療従事者も含め、デジタルリテラシーの格差があります。デジタルツールによって保健医療従事者と医療施設や地域の保健当局などをネットワーク化し、遠隔医療も活用しながら、保健医療従事者の偏在・人手不足による影響を緩和し、NCDsの予防、「ウェルネス」の推進をしていくことが望ましいと言えます。また、そのためのツールを提供する民間企業にとっても、ビジネスとしての価値と社会的インパクトを両立させることに繋がります。
今回の調査を通じて見えてきたのは、日・ASEANでは既に様々な取組が行われているものの、その多くが個別のプロジェクトごとの断片的なものであり、民間セクターとの連携も不十分で、ASEAN地域全体での広がりに欠けているという状況です。上記のような取組のためには、官民の枠を超えた多様なステークホルダーによる対話のプラットフォームが不可欠と言えるでしょう。
セミナーの実施
10月16日、報告書の最終取りまとめ直前の段階で、同調査結果を発表するオンラインセミナーを長崎DrPHプログラムとの共催で開催しました。セミナーには日本やASEAN諸国の第一線で活躍する専門家が参加し、活発な議論が行われました。参加者との討論では以下のようなコメントがあり、これらも踏まえ、上記の調査報告書が取りまとめられました。
- ASEAN諸国においてNCDsの疾病負荷が増大しているが、喫煙や高血圧などのリスク要因を見ても、これらの総死亡率への寄与が高いため、NCDs対策を優先テーマとして取り上げ、相互運用可能なデータ基盤を整備することに賛同
- 東アジア・アセアン経済研究センター(Economic Research Institute for ASEAN and East Asia: ERIA)で行っている、ASEAN諸国及び周辺の国々における、医薬品や保健医療サービスへのアクセス改善や規制調和などに関する研究とも重なる部分があり、今後も有益な議論を重ねていきたい
(参考) ERIA, Healthcare and Ageing Society
- 国によって医療機器等の規制が異なることが市場参入の障壁となっていることを現場で強く感じているため、規制調和を推進することはまさに重要(NCDs早期発見のためのAI活用型画像診断技術を手掛け、ASEAN諸国での市場開拓にも積極的な日本のスタートアップ企業のコメント)
- NCDsは、食や栄養の分野とも関わりが深く、さらにプラネタリーヘルスとも調和するようにフードシステムの改善が必要
- ASEAN諸国も高齢化していることを考慮に入れつつ、テクノロジーの活用においては、アクセスの公平性・公正性についても留意した対話をすべき
- 財政的な裏付けが十分でないと実行可能性に乏しいため、革新的な資金創出方法の検討も含め、財源についての更に掘り下げた分析が必要
グローバルヘルス政策に関する多様なステークホルダーとの対話に関する活動報告
Copyright © Japan Center for International Exchange (JCIE)