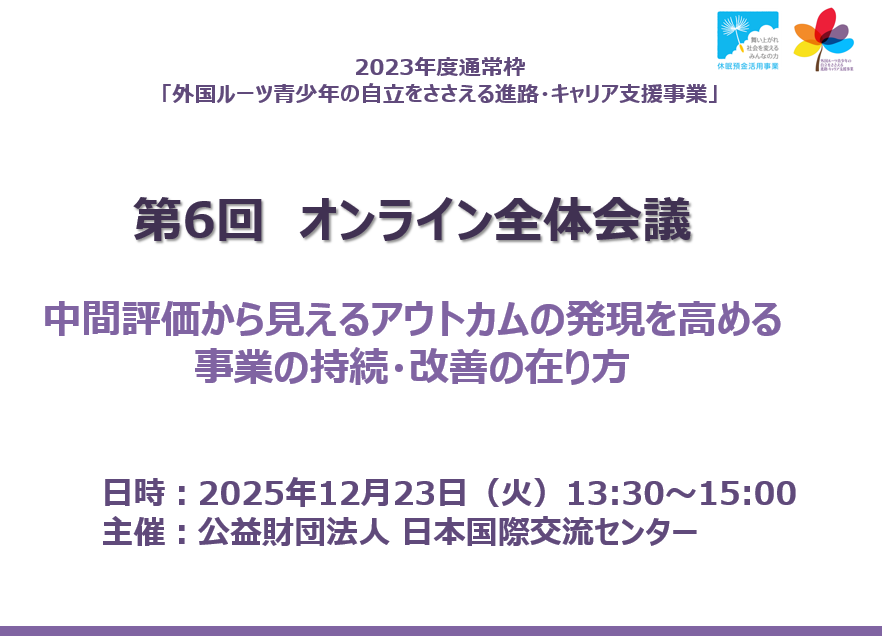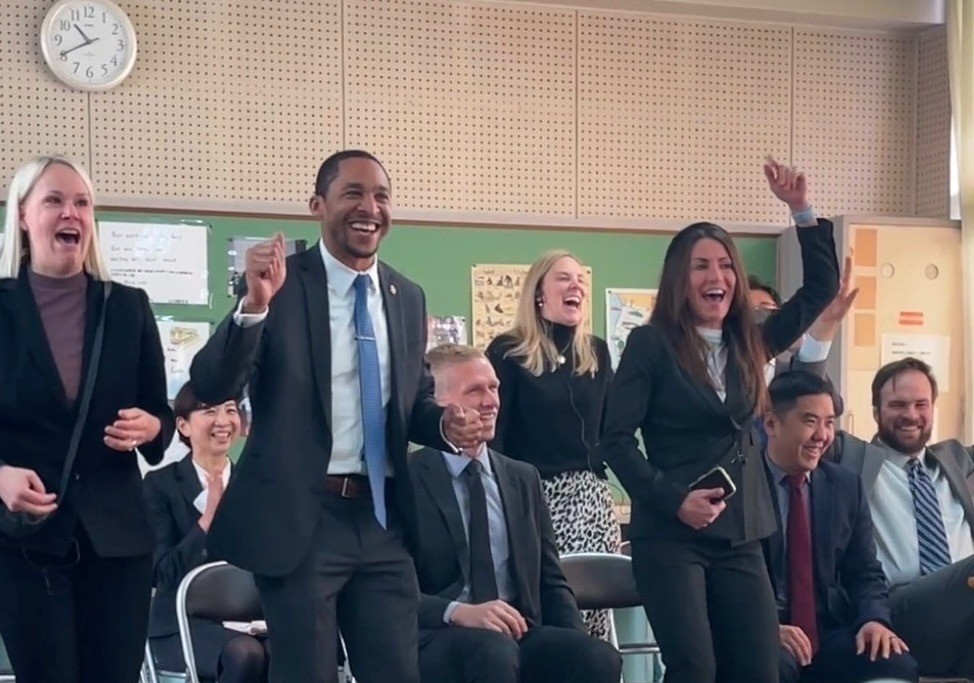ページを探す
ウェブ対談「グローバルな新型コロナウイルス対策:民間寄付が持つ意義」
動画後の数秒間、静止画が続きます。動画開始から23秒後より本編が始まります。冒頭のアンケート結果は、当日オンラインでは画面で表示されていましたがこの動画では表示されませんのでご了承ください。
日本国際交流センター(JCIE)は、2020年7月15日に、ウェブ対談「グローバルな新型コロナウイルス対策:民間寄付が持つ意義」を開催しました。本対談は、新型コロナウイルス危機に直面し、WHOが初めて民間資金を受け入れることとなった「WHOのための新型コロナウイルス感染症連帯対応基金」の立ち上げから4か月の機会の報告を兼ねて開催されたものです。WHO本部から山本尚子事務局長補、そして、日本の寄付文化の専門家である日本ファンドレイジング協会の鵜尾雅隆代表理事をお招きし、JCIE執行理事の伊藤のモデレートにより対談を行いました。
対談の背景
日本国際交流センターは、国連財団(United Nations Foundation、本部・米国ワシントンDC)とのパートナーシップにより、新型コロナウイルス感染症との闘いのための世界規模の募金キャンペーン COVID-19 Solidarity Response Fund for WHO (WHOのための新型コロナウイルス感染症連帯対応基金 | 略称:連帯基金)の日本国内での募金団体としての活動を4月9日より開始しました。
当基金には、7月4日現在、世界から2億2,400万ドルにのぼる多額の金額が寄せられ、日本からも11億円を超す寄付が集まっています。現在、この連帯基金の寄付金は、WHOの新型コロナウイルス対策を支える最大の資金源となり、1つの主要ドナー国に匹敵する規模感・存在感を示しています。また、寄付額を国別で見ると、アメリカの企業と個人が全体の寄付の7割を占めており、WHOの脱退を表明した米国政府とは異なる民意を示しているという興味深い現象も生じています。
こうした背景に基づき、本対談では、WHOが果たしている役割、公的資金と比較した民間資金が持つ強みやコロナ禍における寄付の意義について、対談形式でお話をいただきました。続く質疑応答セッションでは、「寄付は将来的なコロナウィルス感染拡大予防にも役立てられているのか?」「利益相反に関してWHOはどのように管理しているのか?」等、視聴者から数多くの質問が寄せられ活発な議論が行われました。スピーカーの発言の概要は以下の通りです。
スピーカー発言要旨
山本尚子 WHO事務局長補
感染拡大の状況
新型コロナウイルス感染拡大は、世界各国において依然、予断を許さない状況にあり、事態は長期化するであろう。開発途上国の現場では、マスクや手袋、防護服、検査キットなど感染拡大を抑えるために必須の基本的な物資が絶対的に不足しており、これらの物資を感染が拡大する前に早く最前線に届ける必要がある。しかし、これまでのWHOの予算の枠組みでは、それがかなわなかった。連帯基金はそれを可能にした。
民間資金を受け入れた背景
WHOはこれまでは民間資金の受け入れを躊躇してきた。基準やガイドライン作りが活動の大きな柱であるため、特定の民間組織から資金を受けると公平で中立な立場が保てなくなるのではないか、という懸念があるからである。しかし近年、ニーズが多様化しWHOが必要とする予算が急増していている中、各国政府の拠出だけでなく幅広く民間から資金を集めるべきではないかという意見がでてきていた。意思決定や資金の流れの透明性を確保し、ガバナンスを強化すれば、民間から寄付を受け入れたからといって基準やガイドラインがゆがめられることはない。こうした議論の土壌があったところに、新型コロナウイルス感染拡大が後押しとなり、各国のパートナーの協力の下、この度の民間寄付の受入れとなった。
民間資金ならではの特徴
WHOに対する政府拠出の多くは、地域や分野など使途が決まった「任意拠出金」で、柔軟性の高い「分担金」は全体の25%にとどまる。そこに限界も見えていた。民間の寄付金の特徴は、迅速性、柔軟性だ。連帯基金の資金が送られてきたのは4月3日という非常に早い段階であった。初期の段階で手を打てば感染拡大が防げるという意味で初動資金は重要だ。長い歴史を持つWHOという公的国際機関でも危機への対応に限界はあり、この連帯基金という民間の力がその壁を打ち破り、従来のWHOでは出来なかった対応を可能にし、世界の人々の命や健康を守っている。寄付を託される側のWHOとして、責任を持って成果を出していきたい。
コロナ危機は日本人の意識を変えるか?
コロナ危機によって、人々の国際協力への意識は変わるだろう。医療水準が高い多くの先進国が深刻な状況に陥っているのに対し、太平洋諸国など小国でもしっかりと連携し、成果を出している国がある。富める者が貧しい者を救うという一方通行の国際協力の構造が、新たな局面を迎えようとしているのではないか。
鵜尾雅隆 日本ファンドレイジング協会代表理事
コロナ禍での日本の寄付の動向
特別給付金が配られるとなったころから、日本での寄付は増えてきている。最初の頃はマスク配布への支援が多かったが時間が経つにつれ、生活困窮者への支援やアーティストの支援も増えるなど寄付軸が多様化してきている。
日本の寄付の発展
日本の寄付やボランティアは、大規模災害がある度に発展してきた。約130万人のボランティアを生んだ阪神淡路大震災は後に「ボランティア元年」と呼ばれ、国民の約68%が寄付をした東日本大震災は後に「寄付元年」と呼ばれるようになった象徴的な出来事で、その後、ボランティアや寄付行動が定着した。今回のコロナ危機でも寄付が高まっているが、二つの特徴がある。1つ目が、“選択する寄付”である。災害時は、義援金という受け皿があり寄付をすれば被災者に均等に配られる仕組みになっているので、迷わず義援金に寄付をした人が多い。しかし新型コロナウイルス対策では義援金がない中で、初めて自分で寄付先を選択することが求められている。この連帯基金が、安心できる寄付先として選択肢の一つになっていることは大きな意味がある。2つ目の特徴が、医療関係への寄付が大幅に増えている点である。欧米では多いが、日本社会では、初めて生じた寄付の流れである。
民間資金の強み
政府だけでは手が回らない社会問題があり、税金を原資にするとどうしても平等にならざるを得ないところ、民間資金はニーズに応じて柔軟に対応できる。政府の対策と比較した民間資金の強みとして3つある。1つ目が、政治的意思に左右されない持続性、2つ目が、先例がない新しい試みにチャレンジできる実験性、3つ目に、まだ顕在化していない社会課題に取り組み可視化することによって、現場と社会を繋ぎ、共感を呼び起こしていくことである。民間のおカネでまず応援し顕在化し、やがて行政の支援とつなぐパイプラインの役割を果たすことができる。
コロナ危機は日本人の意識を変えるか?
コロナ危機により、困難な立場に置かれている人や海外の課題に対する共感性が増えてくる可能性がある。ソーシャルセクターは、海外との心理的距離を縮める努力をする必要がある。その意味で、寄付は、国境を超えて人をつなぎ合わせる共同作業だともいえる。「寄付は投票である」との言葉がある。寄付は個人の価値観に基づいて自分の欲しい未来を選択するための行動だ。WHOが新型コロナウイルスとの闘いに奮闘する中で、連帯基金へこれ程の寄付が集まっていること、つまり、「支持している」という投票行動があったということに、非常に勇気づけられる。
WHOのための新型コロナウイルス感染症対応連帯基金
日本国際交流センターは、国連財団(United Nations Foundation、本部・米国ワシントンDC)とのパートナーシップにより、新型コロナウイルス感染症との闘いのための世界規模の募金キャンペーン COVID-19 Solidarity Response Fund for WHO (WHOのための新型コロナウイルス感染症連帯対応基金 | 略称:連帯基金)の日本国内での募金団体としての活動を4月9日より開始しました。

グローバルヘルスと人間の安全保障に関連する活動報告
Copyright © Japan Center for International Exchange (JCIE)