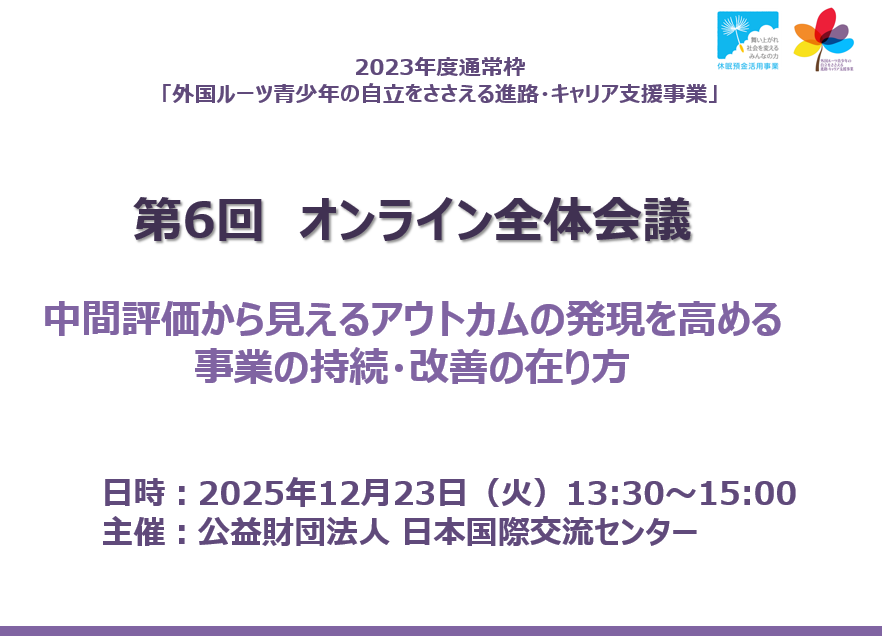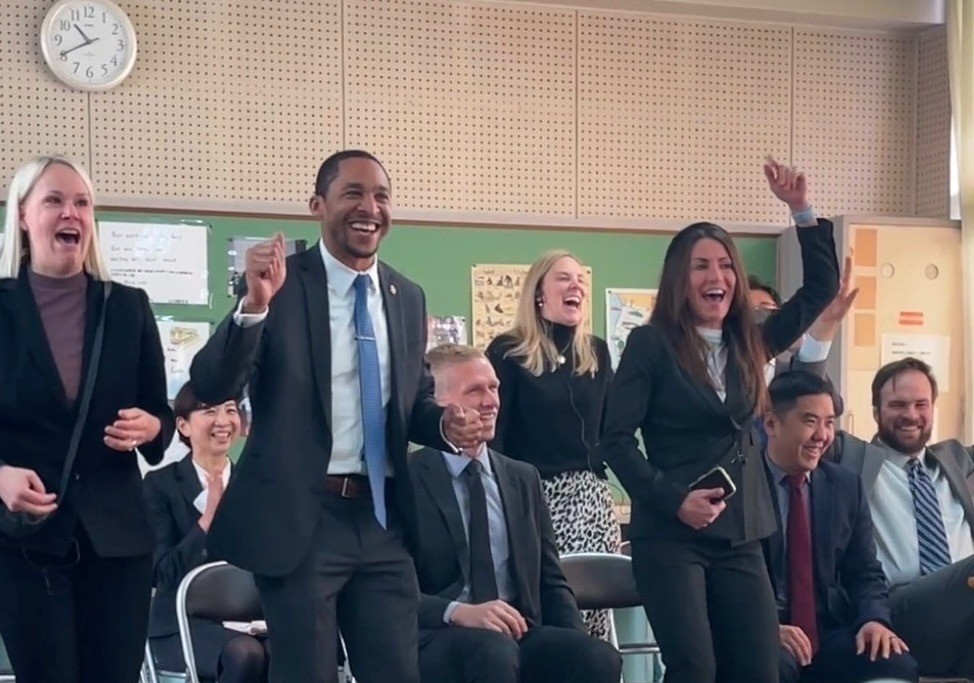ページを探す
外国ルーツの若者のキャリア支援プログラムを組み立てる:キャリア支援事業 第4回連携会議
日本国際交流センター(JCIE)は、2025年3月12日、「外国ルーツ青少年の自立をささえる進路・キャリア支援事業」の一環として、第4回連携会議を開催しました。本会議では、当該事業採択5団体が、「外国ルーツの若者を対象としたキャリアプログラムをどう組み立てるか」をテーマに、「外国ルーツの若者」、「支援者」、「社会構造」という3つの要素を踏まえて、実践の中での課題とその改善、解決に向けた視点は何かについて議論を行いました。
最初に、働き方評論家として活動されている常見陽平氏が、日本社会におけるキャリア形成を取り巻く構造について発題をしました。常見氏は、生産年齢人口の減少という社会構造、働き方や価値観の多様化に対応しようとする企業社会の変化をとらえつつ、多様な選択肢の提供、ワークルール教育の強化などを通じて「就職支援」から「キャリア形成支援」へ、「働く」だけでなく「よく生きる」ための支援へシフトしていくためのプログラム作りの重要性を延べました。
常見氏の発題を受けて、採択団体の一つである認定特定非営利活動法人カタリバから、外国ルーツの高校生を支援する「Rootsプロジェクト」の取り組みを行う中で見えてきた、外国ルーツ青少年のキャリア支援に向けた地域でのエコシステムをつくるうえでの企業とのビジョンづくりにおける課題とともに、インターンシッププログラムへの参加による企業側の変化を共有しました。

前半の問題提起を受けて、後半はグループに分かれ、現在のプログラムの組み立て方や、その中で感じた悩みや手応え、社会全体を巻き込むようなアクションの方向性について議論を行いました。外国ルーツ青少年として自分の前提を説明することの難しさとその背景にある外国人をとらえるステレオタイプの存在、「日本人と外国人」というカテゴリー化による社会の認識の固定化、親と子供など世代間の認識、理解の違いなど、外国ルーツ青少年のキャリアプログラムを形作るうえで見えにくい要素が指摘されました。また、大学や企業による「人」を確保するための工夫がなされ、選択肢が広がっている現状がある中、支援する側として常に変化する可能性を追い切ることや、インターンシッププログラムなど学校、企業と連携したプログラムの実施による企業側、学校側の意識・体制の変革が重要であるといった意見も共有されました。
グローバルな人の移動に関連する活動報告
Copyright © Japan Center for International Exchange (JCIE)